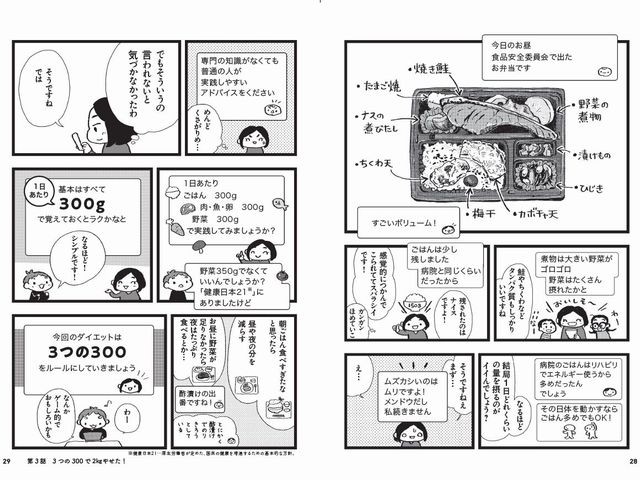「迷子は時間の問題」と医師に言われた父が、GPSを拒否します【お悩み相談室】
構成/中寺暁子

認知症介護指導者の久保圭司さんが、認知症の様々な悩みに答えます。
Q.父(80代)はもの忘れ外来に通っていて、医師から「いつ迷子になってもおかしくない」と言われました。そこで、キーホルダー型のGPSを買ったのですが「監視されてイヤだ」と拒否されました。どうすればいいでしょうか(50代・女性)
A.私自身グループホームなどで長く働いているなかで、何度か利用者の方が気づかないうちに出て行ってしまい、探し回ったということを経験しています。いずれも大事にはいたりませんでしたが、ここから先は行かないだろうと思うようなエリアで見つかったということもありました。相談者がお父さんを心配するお気持ち、よくわかります。
ただ、お父さんの「監視されてイヤだ」という主張も、理解できます。ご本人としては行動を制限されているように感じるのかもしれません。避けたいのは無理にGPSをつけられたり、外出に関して何度も注意されたりすることで、外に出たいという意欲が低下してしまうことです。認知症の進行やBPSD(行動・心理症状)の悪化につながるリスクがあります。
GPS内臓の専用シューズを用意したり、いつも着ている上着や持ち歩いているカバンにこっそりGPSをしのばせておいたりすることもできますが、理想としては本人が納得したうえでGPSを持ち歩くことだと思います。お父さんはもの忘れ外来に通っているとのことなので、ご本人としてもある程度もの忘れがあることを自覚していて、それを何とかしたいというお気持ちもあるのかもしれません。それであれば、医師のほうから「お守り代わりに持ってくださいね」「娘さんが安心して過ごせると思いますよ」というように、GPSをすすめてもらうと効果的ではないでしょうか。お父さんのいないところで、医師に相談してみるのも1つの方法です。
ほかにできることとしては地域とつながりを持っておくことです。地域包括支援センターや民生委員にいまのお父さんの状況を伝えておくといいと思います。地域によっては見守り活動を積極的に実施しているところもあります。
また、お父さんはどのような場所に出かけているのか、普段の行動を把握しておくことも大事です。迷子になるのは、ある日突拍子もなく見知らぬ地域に出かけて起こるというよりも、公園や商店街など普段から通っている場所に行ったつもりが、道がわからなくなってしまったという状況であることが多いと思います。万が一のことがあっても、普段の行動範囲を把握できていると見つけやすいのではないでしょうか。
こうした対策によってお父さんの意思を尊重しつつ、相談者自身も安心して過ごせるといいですね。
【まとめ】もの忘れ外来に通う父が、医師から「いつ迷子になってもおかしくない」と忠告されたのにGPSを拒否するときには?
- もの忘れ外来の担当医から、GPSの携帯をすすめてもらう
- 地域包括支援センターや民生委員にお父さんの状況を伝えておく
- 普段のお父さんの行動範囲を把握しておく
≪お悩みの内容については、介護現場の声を聞きながらなかまぁる編集部でつくりました≫