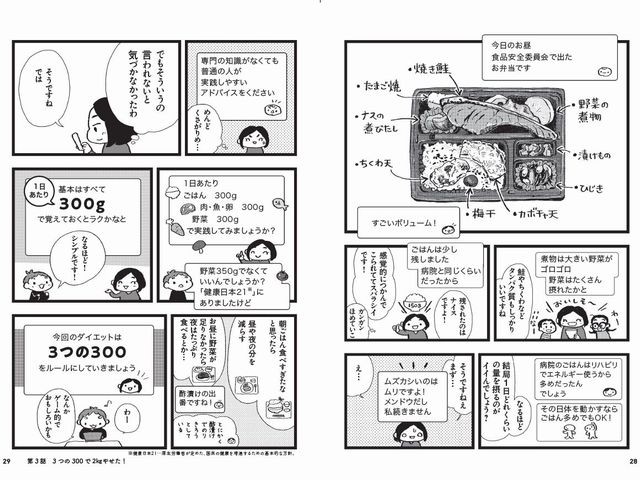「認」め合い「知」ること

こんにちは
若年性認知症当事者のさとうみきです。
皆さんは、なかまぁるのたくさんの方々の連載や記事などをご覧になって、
認知症をどのように捉えていらっしゃいますでしょうか?
私は、認知症当事者としての様々な活動を通し、たくさんの経験をさせていただいています。
そうした活動で、仲間たち(認知症のあるご本人の方々)とともに過ごす中で感じていることをお伝えさせていただきたいと思います。
これはあくまでも私個人の意見かもしれません。
認知症=記憶障害。
そんなふうに一般的な知識で、
「何もかもがわからなくなってしまう…」と、
感じている方も多いかもしれません。
しかし、私たちの症状は、一概には言えません。
記憶障害だけではない様々な症状があります。
私のように、記憶障害が目立つわけではないものの、
生活のしづらさにつながる別の症状があることを、まだまだ知られていない現実があります。
その一つが、手元や足元の空間の認識のしづらさです。
必死に手すりを持とうと思っていても、距離感がわからないのです。
周囲の人やご家族からしてみたら
「なぜそんなこともできなくなってしまったのか…」と、
そんな疑問に感じるかもしれません。
しかし、私たちは、そうした認知症という空間で、自身が体感している世界の中で、必死に生きているのです。
そして、みなさん、認知症という色眼鏡で私たちを見ていませんか?
どんな状況になっても、
その人となり、その人らしさ、私は私であるということは、
認知症の診断を受ける前と同じように変わらずあるのです
認知症の誰々さんとして、出会い、見るのではなく
目の前のひとりの人として、接していただきたいのです。
認知症とは、
ありのままを「認」め合い
目の前のその人を「知」ること。
そうすれば、「偏見」という大きな「壁」がなくなるのではないでしょうか。
仲間たちとの出会いから、
そして、自分自身の経験からもお伝えしたい今の気持ちです。
それは、認知症の私たちだけではなく
何らかの病気や障害をお持ちの全ての方にとっても同じことが言えるのかもしれません。