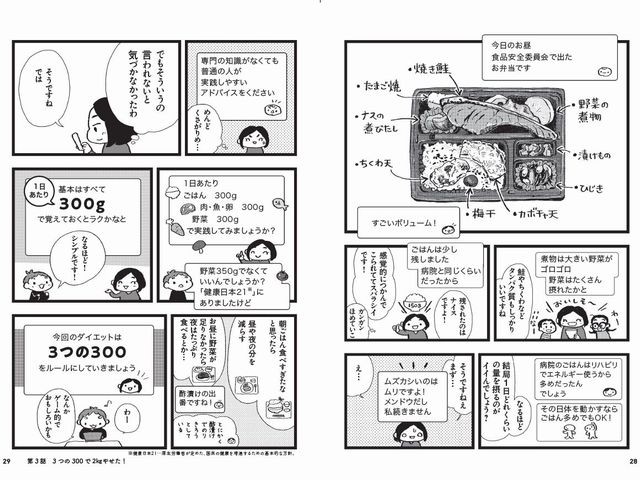「わかる?」「できない?」 やさしい問いかけも私にとってはNGワード
《介護福祉士でイラストレーターの、高橋恵子さんの絵とことば。じんわり、あなたの心を温めます。》

うーん。
この味つけには、どっちかな?
調味料とにらめっこしていたら、
パートナーがとんできた。
私が認知症と診断されてから、
彼はいつもこんな感じだ。
「わかる?」
そう言われると、なぜか、
わかっていることも混乱しそうになる。

急なスマートフォンへの着信。
早く出なきゃ!と慌てた指先は、画面をさまよう。
落ちつこうと息を整えていると、
また、慌てたあなたから、
「できない?」の問いかけ。
そう言われると、緊張が走り、
私にはできないとしか、思えなくなる。

私が困らないように、と
いつもやさしいパートナー。
でもごめんなさい!
「わかる?」「できない?」は
これからNGワードでお願いします。
うまくできないかもしれない。
そのもどかしさに、一緒にいてくれるだけで、
私は安心なのよ。
「わかります?」
「できます?」
そんな、白黒つけるような問いかけは、相手の心とからだを一瞬にして緊張させます。
けれど、このやりとりが、
認知症がある人と、となりにいる人との間でよく聞こえてくるのは、
「スムーズにうまくできないことを認めあう空気」に、
私たちが慣れていないからではないでしょうか。
健康であるとき、私たちは、
なんでもスムーズにできるのが当たり前、という雰囲気の中で生きています。
でも、高齢になったり、認知症が出てきたりすると、
そのスムーズさはなくなっていきます。
それこそ、
ポケットからハンカチを出して、
ハンカチを広げて、
手を拭く。
そんなたやすく見える行動も、
実は細かな動作と、記憶と理解の重なりを経て行われているのですが、
健康なうちは、気づくよしもありません。
つまりどんな行動も、おおざっぱに、
「できる?」
「わかる?」と
白黒つけて、判断できるものではないのです。
認知症がある人が、
スムーズに行動できないとき、
ご本人も、となりにいる人も、
独特のもどかしさを味わいます。
でも、そのもどかしさを振り払わない心持ちこそ、
私たちに必要な在り方ではないのでしょうか。
誰もがいつか、ままならない体と付き合っていく、
日常が待っているのだから。
《高橋恵子さんの体験をもとにした作品ですが、個人情報への配慮から、登場人物の名前などは変えてあります。》