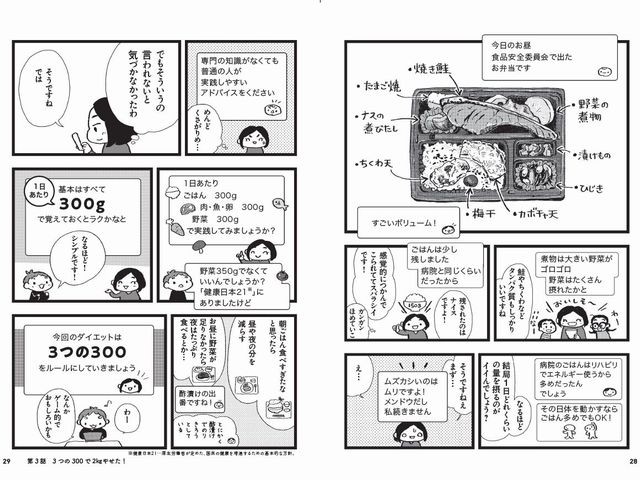「こちらの都合は二の次」時代に始まった介護と仕事の両立生活

タレント、キャスターとして活躍する“コマタエ”こと駒村多恵さんが、要介護5の実母との2人暮らしをつづります。ポジティブで明るいその考え方が、本人は無意識であるところに暮らしのヒントがあるようです。今回は、母親が要介護であることを誰にも告げずに、仕事と介護を両立していたころのお話です。
東京都シンポジウム
先日、東京都の介護と仕事の両立推進シンポジウムに参加しました。
法改正に伴い、令和7年4月1日からは、介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となります。また、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供や、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにすることが努力義務となります。今回は管理職や労務担当の方向けのシンポジウム。そこで、普段私が仕事をしながら介護をする日々の始まりから現状の工夫の一端をご紹介しました。
母に介護が必要とわかったのは約17年前。当時私は朝5時20分からの生放送の情報番組の中でエンターテインメントコーナーのキャスターをしており、俳優、アーティスト、芸人さんなど、様々な方へのインタビューを担当していました。

当日朝の出演もですが、ロケに行くこともしょっちゅう。ロケは相手方のスケジュール次第で、だいたい急に決まります。北野武さんがベネチア国際映画祭に行くという情報を得たら、「とりあえずベネチアに行って、何か撮ってきて!」ということで突然旅が決まったり、マライア・キャリーの来日インタビューが取れるということで行ってみたら、「マライアが遅れていて、8時間後になっちゃいます」と大幅な時間変更を余儀なくされたことも。大変やりがいがあったものの、こちらの都合は二の次という働き方で、今の時代には考えられませんが、当時はそれも当たり前という感覚でした。


そんな最中の介護宣告。仕事はどうする!?と真っ先によぎりました。が、幸いなことに、当時の母はそれほど深刻な状態ではなく、主治医の先生も「認定調査をしても要介護1だろうから、今、認定を取らなくてもいいんじゃない?」というご意見だったので、デイサービスに行く代わりに、認定を取らなくても参加できる、自治体が運営する介護予防教室や体操教室の情報を区民報で見つけては応募し、母が活発に過ごす機会を積極的に作る努力をしました。私がいなくても見守ってもらえるのと同時に、毎日暮らしているだけでは見逃してしまうかもしれない母の変化を客観的な目で見てもらえるというのは、今振り返ってみても良かったように思います。そうこうしているうちに、番組が終了。結局、母のことは、一緒に働くスタッフの誰にも話すことはありませんでした。


今でこそ、どなたかの介護のヒントになることがあればと、母との日々を綴っていますが、当時は公表なんてもってのほか、周囲の同僚に介護をしていることを打ち明ける気すら、毛頭ありませんでした。プライベートと仕事は別物で、プライベートで何かあってもそれが画面上でわかるようであれば、プロとして失格だし、そもそも介護をしていようがしていまいが、仕事には全く関係ないこと。誰にも話す必要などないと思っていました。しかし、介護度が上がると、どうしてもこれまで通りにはいかなくなる場面が訪れ、やむをえず仕事に影響が出てしまうとわかった時は、一瞬心が折れそうになりました。

誰にも打ち明けることなく介護と仕事をしている人は、実は潜在的に多いのではないかと思います。ひっそりと介護をしている人の心が折れそうになった、あるいは、折れた瞬間、離職を申し出るのではないかと。
厚生労働省の、「企業のための仕事と介護の両立支援ガイド」によると、家族の介護や看護による離職者数は約10万人存在し、今後も離職者が増加することも懸念されるとのことですが、そうなる前に相談、あるいは、相談までいかない雑談を繰り返す中で防げないものかと思います。企業も人材を大切に考え、両立できる環境整備を進められることを期待します。