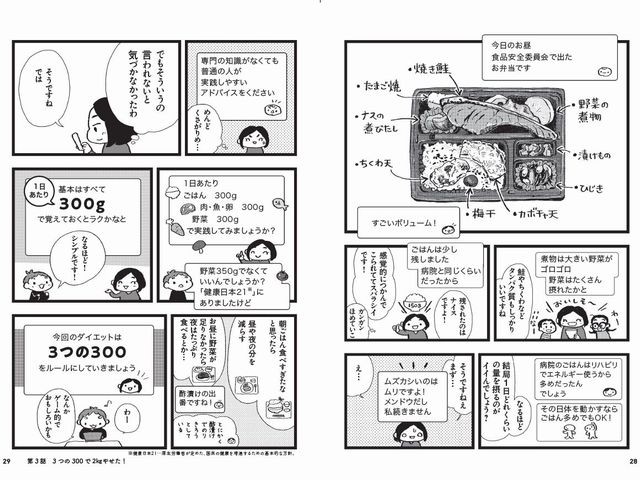認識をひっくり返す セカンドライフに全力投球 台湾の高齢者前編
取材/丸山僚介(KIITO)

高齢化が進む社会への取り組みを、クリエーティブの視点から考える活動が神戸で行われています。なかでも注目されたのが、台湾における高齢化社会のユニークな施策をリサーチし、2019年にデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)で開催された「LIFE IS CREATIVE展」でした。この展示のリサーチを担当したKIITOの丸山僚介さんに、台湾の取り組みの面白さを紹介していただきます。
台湾の「LIFE IS CREATIVE」な活動との出合い
私たちは神戸で「LIFE IS CREATIVE」という高齢化社会問題をクリエーティブに解決する試みを、2015年の展覧会企画からスタートさせました。展示と並行して立ち上げられたいくつかのプロジェクトは、現在も継続しています。2019年度には「LIFE IS CREATIVE展2019(以下、LIC展)」を開催し、継続しているプロジェクトの経過報告と、新たな展開として海外の先進事例をリサーチし紹介する場を設けました。

このLIC展に向けて海外の先進事例をリサーチしていたところ、「台湾には高齢者の認識をひっくり返すような取り組みがいくつもありますよ」と、台湾・台中市の東海大學の李俐慧(リー・リフィ)准教授から紹介いただいたことをきっかけに、日本と同じく超高齢化社会が進行する台湾の先進事例を集めることになりました。すると見えてきたのは、ワクワクする高齢化社会の未来の姿でした。
余生を全力で楽しむのが台湾スタイル
リサーチをするなかで、台湾の方にとって「セカンドライフ」と捉える人生のフェーズは日本よりも早く訪れているということがうかがえました。日本ではセカンドライフは定年後(60~70代)を指すことがほとんどですが、台湾では多くの方が子供のひとり立ちするタイミング(40~50代)を区切りとし、セカンドライフを有意義に過ごすための新たな役割や趣味などを積極的に考え、その下準備に取り組んでいるのです。

社会を支えることが、人生を豊かにする
台湾の老人ホームの多くは基金会(日本でいうところの財団)が担い、民間企業がその運営を支えています。このことから若い世代の方々は高齢者を支えている自負が強くあり、高齢者になっても「自身の力を社会に生かすこと」がセカンドライフを充実させるための重要なファクターになっていました。
高い予防意識
このように、若い年齢から自身の高齢化に意識を向け、行動に移す早さには目を見張るものがありました。さらにお話を伺っていくと、セカンドライフの充実は「認知症予防ともいえる」という声も多く聞こえてきました。
このリサーチをしていくなかで、
1. 役割を持つこと
2. 身体を動かすこと
3. 新しい力を身に付けること
4. 人とコミュニケーションをとること
この4つの積み重ねが心豊かなセカンドライフを育むこと、そして健康寿命を延ばすことにつながるという意識を強く持っているということがわかってきました。

この4つに視点を置いて、いくつかの台湾のアクション事例を紹介します。
事例1 遠のいてしまったかつての夢を叶える、台湾1周のバイク旅 「不老騎士(ふろうきし)」

弘道老人福利基金会が営む老人ケア施設を利用する1人の男性が、「バイクで台湾を一周したかった」というかつての夢をスタッフに語りました。島国とはいえ、一周1,178km(東京~福岡くらい)もの距離があり、容易ではありません。しかし、そのときスタッフは「若かったらできた」という考え方が人を老いさせてしまっているのでは? と思いを巡らせ、高齢者のためのバイクツアー企画を打ち出しました。体力を考慮した旅程計画、旅中の警察や医療機関のサポート取り付けなどの調整を重ね、公募で集まったシニアたちに向けたツアー前のトレーニングも徹底的に行い、ツアーは現実のものとなりました。
「若くない」という自負が自らの可能性を狭めていることを浮き彫りにしたこの企画は台湾国内で大きな反響を生み、映画化されるまでの広がりを見せました。

この企画は他ジャンルへも広がり、野球、演劇、サーフィンなどが企画され、おのおのの夢が実現できる場が生まれています。多くのシニアに勇気を与え、新たな活力を生み、体力の維持・向上に取り組むきっかけとなりました。
事例2 家族に作り続けた味を披露できるレストラン「食憶(しょくおく)」

台湾は、中国人が住まい始めるよりも昔から、東南アジア各国からの移民が暮らす多民族国家であり、小さな島ながらも多様な食文化が根付いています。そんな台湾の家庭料理に着目したレストランが「食憶(しょくおく)」です。

食憶で調理を担当するのは全員シニアです。彼らにとっては、子どもたちが巣立って作る機会の減ってしまった料理の腕を披露するための場となっています。
そこで提供される料理は彼らがこれまでの人生で作り続けてきた家庭料理ばかり。また、それぞれが親子代々引き継いできた料理は、異なる国の料理から派生したもので、それぞれのストーリーを持っています。
この「食の記憶」を料理と言葉でお客さんに伝える場が「食憶」です。

このレストランが秀逸なのは営業の仕組みです。現在20人ほどのシニア料理人が在籍しており、各自がスマホで勤務希望日を登録します。一営業日につき3人の料理人が決まるとその日だけが営業日となるので、自身の都合に合わせた働き方が可能となっています。
事前決済の完全予約制で、食事開始時刻が決まったコースディナーのみというスタイルのため、仕入れや料理を出すタイミング、料理についてのストーリーテリング、閉店時刻まで、全てが事前想定可能で、経営においてのストレスが料理人らに課せられることはありません。また、その日の料理人やメニュー内容は来店するまでは明かされないため、急きょの事態も営業に支障が出づらく、常に「料理人ファースト」の業務形態です。
「食憶」という仕組みはシニアの新たな役割を創出し、仲間を得る場、そしてお客さんとの交流ができる場ともなっています。
後編へ続く
デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)のプロジェクト「LIFE IS CREATIVE」についてはこちら

- 丸山僚介(まるやま・りょうすけ)
- 2014年よりデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)勤務。「+クリエイティブ」をコンセプトに社会的課題の解決を目指すさまざまな活動や、レクチャー、ワークショップ、展示などの企画運営を行なう企画事業部のチーフスタッフを務める。2019年度に開催した「LIFE IS CREATIVE 展 2019 高齢社会における、人生のつくり方。」にて台湾の先進事例のリサーチ、展示を担当した。