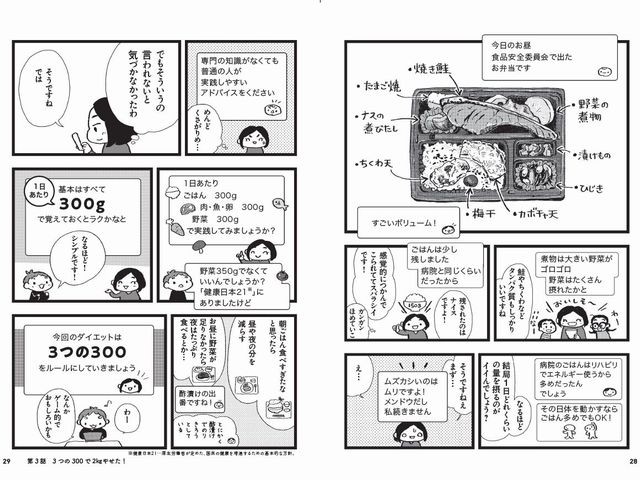薬より前に、認知症の本人の話を聞くことの大切さ 心の戻る力を信じて

認知症について知っておきたい基礎知識について、榊原白鳳病院(三重県)で診療情報部長を務める笠間睦医師が、お薦めの本を紹介しながら解説します。
かつて認知症の外来では、医師が本人からではなく付き添ったご家族から詳しい経過を聞いて問診を進め、その後、簡易な認知機能検査を本人に実施したうえで画像検査を行い、診断をしていくのが一般的な診察風景でした。
特に、認知症の行動・心理症状(BPSD)については、現在でもご家族からの情報収集が中心となっているのが現状ではないかと思います。
東京都三鷹市の「のぞみメモリークリニック」院長の木之下 徹先生が、「薬でコントロールする前に当事者、本人の話を聞くべきではないか。」と問題提起されていますのでその記述をご紹介したいと思います。
- 多くの人は認知症を、そして認知症になることをおそれている。
「認知症になると、壊れるの? おしまいなの?」
どう答えるか?
「おしまい」とは死ぬことを意味するのか?
「おしまい」ということについて、誰も説明できない。
「壊れる」=「おしまい」なのか?
「おしまいになる」のではなく、他人が「おしまいにしている」。
薬でコントロールする前に当事者、本人の話を聞くべきではないか。本人はなぜ怒っているのか。家族の話だけ聞かずに、本人の視点で考えるべきではないか。周囲の人が、本人の話も聞かず、「ひと」扱いせずに、「おしまい」にしてしまってはいないか。
「おしまいになる」のではなく、自分で「おしまいにしている」。
本人は「生きている価値がない」と思っている。自ら、孤独の闇にただよい、自ら、希望も失い、自らを「おしまい」にさせていないだろうか。これらの問いに答えなければならない。
【編/佐々木淳 著/木之下 徹『在宅医療カレッジ─地域共生社会を支える多職種の学び21講』,医学書院, 2018, p9-10】
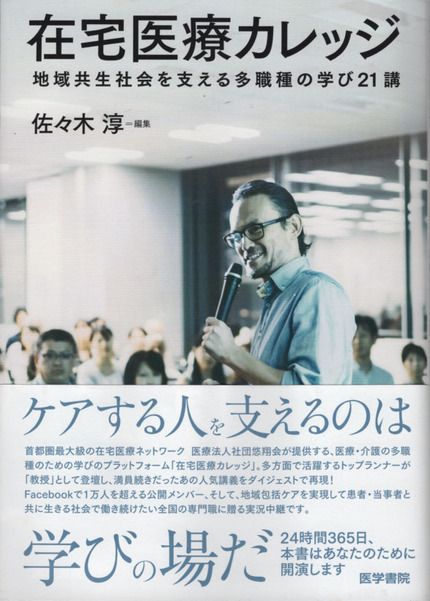
39歳の時に若年性のアルツハイマー病と診断された丹野智文さんも、認知症を取り巻く現状について疑問を投げかけています。「認知症になると何もわからなくなってしまう」という間違った認識をもつ人が多いために、認知症と診断された人は、「守られなければならない存在」となり、自身の主体的な行動が奪われてしまっているというのです。
さまざまな活動を通して、多くの認知症の当事者と出会い、一緒に行動し、活動するようになった丹野さん。そのなかで、一緒に活動している仲間が急に施設に入所したり、精神科病院に入院したりするということを経験してきました。そのようなとき、「なぜ、入所や入院をする必要があったのか?」と疑問に感じるといいます。一緒に活動しているときには、症状は確かにありましたが、本人の状況を理解し、適切なサポートがあれば、何の問題もありませんでした。そのような人でも、気がついたときには、施設や精神科病院に入れられているというのです。
- 私は、施設や病院に入った仲間に会いに行きました。すると、認知症の症状が、よくなっているどころか、反対に悪化していました。表情も無表情で、すべてをあきらめているようでした。そして、みんな「ここから出たい、家に帰りたい」と話します。その理由は、入院するときに「いつまで入院しなければならないのか」「どのような理由で入院するのか」「どのような治療をするのか」などについて、本人には説明がないためです。
【編著/矢吹知之・丹野智文・石原哲郎『認知症とともにあたりまえに生きていく─支援する、されるという立場を超えた9人の実践』,中央法規, 2021, p29-30】
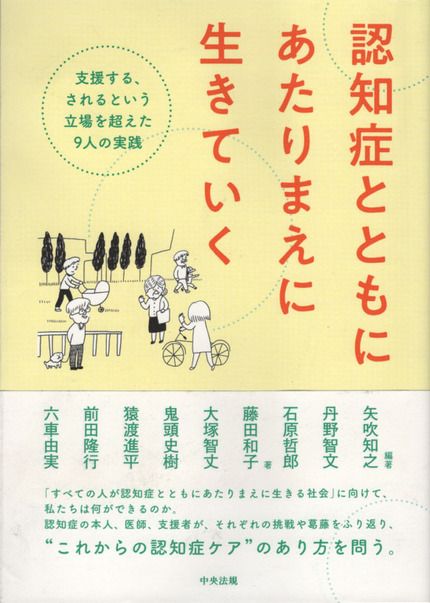
このような現状のなかで、薬でコントロールする前に当事者、本人の話を徹底的に聞く診療を実践する姿を如実に描いた本が2024年に出版されました。
筆者である繁田雅弘先生は東京慈恵会医科大学精神医学講座教授を2024年3月で退官され、2024年6月3日からは栄樹庵診療所(神奈川県平塚市)で診療されています。退官前に書かれたのが、『アルツハイマー型認知症の人との対話 認知症の精神療法2』と『認知症の人の家族との対話 認知症の精神療法3』の2冊です。
最初に『アルツハイマー型認知症の人との対話』という本のタイトルを目にしたとき、深く込み入った話はなかなか困難なのではないかというのが私の受けた第一印象でした。
しかし読み進めてみると、驚くべき対話の実践が書きつづられておりました。
アルツハイマー病の精密検査の結果が陽性でアルツハイマー病の可能性が限りなく高まった43歳の男性が「生きる意味があるのかな」ってこぼしたひと言に対して、治療者(=繁田先生)は「心の中には戻る力があるので、それが自然に舵を切ってくれると思います」と語りかけたのでした(p32)。
また、一部上場企業の管理職を定年退職して間もない61歳の男性(もの忘れを主な理由として自分から大学病院を受診し、若年性アルツハイマー型認知症と診断)と治療者である繁田雅弘先生との対話も印象深いものでした。
- 本人 そんなにカッコよくないですけど、家族の気持ちがわかったというより、家族のことをいろいろと考えるような自分になれたことがよかったって思うんです。
治療者 いいですね。
本人 幸せだと思います。
治療者 幸せ? 認知症になって?
本人 そう認知症になって幸せだと思うんです。家族になれましたし。
(中略)
治療者 認知症になっても幸せとかよく言いますけど、あなたのように認知症になってからのほうが幸せだという人は初めて。
本人 幸せって言っても楽しいとか嬉しいとかではないです。認知症は苦しいです。つらいですけど、人との関係を通して自分というものを知ることができるのは幸せなことではないでしょうか。
病気や障がいをもつことが、自分という存在の本質的な理解につながる人たちがいる。
【著/繁田雅弘 『アルツハイマー型認知症の人との対話 認知症の精神療法2』, HOUSE出版, 2024, p289-290】
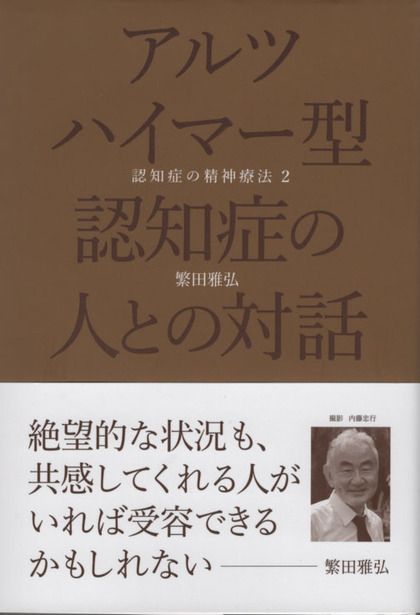
実は、私自身も心を病んだ経験があります。それゆえに〝心の中には戻る力がある〟ということは実感として理解できます。
そのころ、私は、重度のうつ状態に陥り、通常どおり仕事を続けることが困難となりました。日常生活にも困難を極め、自身のSNSなども閉じてしまいました。
その悪夢の2年7カ月にたった一つだけ良いことがありました。妻が、「もう仕事休んだら! 私がアルバイトをすれば食べていくだけなら何とかなるでしょう」と言ってくれたのです。
あのひと言があったので、メンタルを病んだ期間も決して悪くはなかったかな、と今では感じています。
次は、しばしば攻撃的な言動が突出する79歳の独居女性(アルツハイマー型認知症)の事例です。抗精神病薬について本人と家族に説明し、本人が服薬を希望したので「いつでも中止してよい」と指示したうえで投薬を開始します。
しかし服薬を開始してから2週間後の再診の際に、治療者(=繁田先生)は「死亡率も少し上がるんです」と初診時に伝えなかったことを本人に謝ります。そして、本人に対して、抗精神病薬を継続するかどうかは「あなたが決めてほしい。あなたの判断を尊重したい」と伝えたのです(p198-202)。
私自身は医師として、もしものときのために、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有するアドバンス・ケア・プランニング(advance care planning:ACP。「人生会議」の愛称でも呼ばれています)に積極的に関わってきました。本人の意向を確認できる段階で告知を行うことで認知症の人におけるACPを実践してきたのです。そんな私でさえ、抗精神病薬の服薬に関しては、本人の意思(判断)によって治療方針を決定した経験はありません。すなわち、認知症の人に対する抗精神病薬の投薬に関しては、家族からケアの状況を聞いて、介護崩壊を避けるために致し方ないなと判断した際には、家族との相談の中で投薬するかどうかを決定してきたのです。
ここでもう一度、木之下 徹先生にご登場いただきます。前述の本の中で、次のように語っています。
- 「誰のための医療か?
本人の話を聴くこと。それは当たり前のこと。
どういう状況であれ、あえて本人と話すべき。
それがすべてのスタートになる。」
【編/佐々木淳 著/木之下 徹『在宅医療カレッジ─地域共生社会を支える多職種の学び21講』, 医学書院, 2018, p10】
一方で、繁田先生は、『認知症の人の家族との対話 認知症の精神療法3』の「はじめに」において、昨今、当事者として活発に行動する人による啓発活動によって、専門職の視線が認知症の介護者から本人へと向くようになっていると指摘した上で「最近の私の視線はあらためて家族に向き直っている」と、本書を出版した背景を語っておられます。
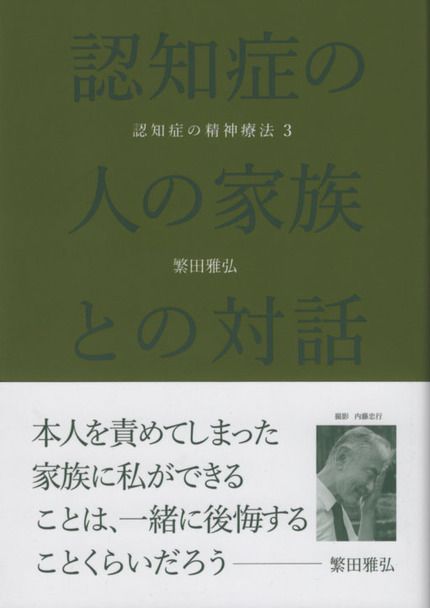
こんな夫妻のお話が出てきます。59歳の夫は、7年前にアルツハイマー病であることを示唆するアミロイドPET検査が陽性であったにもかかわらず、そのことを家族に話さず一人で抱え込んでいました。妻は診察室で、「せめて一緒に受け止めたかったです」「せめてそばにいてあげたかったと思います」と後悔の念を語ります。その時、繁田先生は、こんな言葉掛けをしました。
「奥様を見て安心しているのだと思います」
「病院に通ったり薬を飲ませたりすることが療養ではなく、一緒に向き合うことが療養生活だとわかっていらっしゃるから」
そして、きっと奥様に感謝しているから、奥様からも本人への感謝の気持ちを言葉をいちいち言葉にして伝えるようにと勧め、一緒に外食してはどうかと提案したのでした。
この事例の紹介を通して繁田先生は、「家族は本人の変わったところにばかり目がいくものである。私たち医療・福祉の専門職は、本人の変わっていないところを家族が見失わないように支えなければならない」と我々専門職に家族ケアの極意を示してくれます。
認知症の本人に対するケアの本は数多く出版されておりますが家族に対してどのような言葉掛けをするのが望ましいのかを教示してくれる本は珍しくとても貴重です。
このケースの他に、虐待に及んでいる家族に対する繁田先生の毅然(きぜん)とした対応を描いた珍しい事例紹介などもあり、ぜひとも多くの方に手に取って読んで頂きたい一冊です。