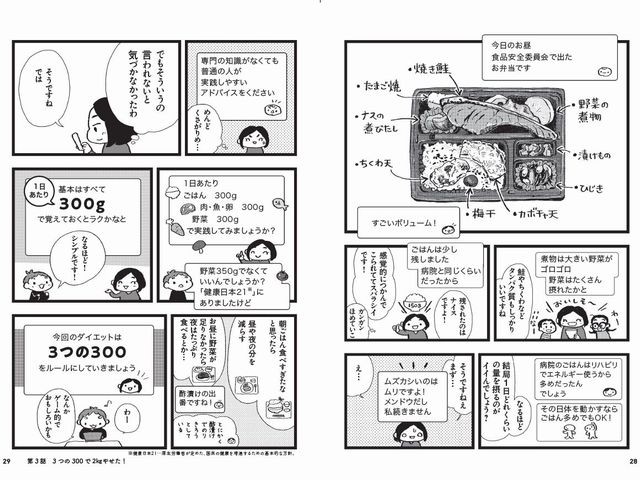変わった介護職へのイメージ たたき込まれた基本精神 初任者研修を終了

新卒で入社した出版社で、書籍の編集者一筋25年。12万部のベストセラーとなった『87歳、古い団地で愉しむ ひとりの暮らし』(多良美智子)などを手がけた編集者が、40代半ばを目前にして、副業として訪問介護のヘルパーを始めることを決意しました。働き始めるために必須とされたのが「介護職員初任者研修」の受講。1ヵ月の自宅学習期間と10回にわたるスクーリングを経て、いよいよ研修が終了です。
2回の実技テストを経て、最終日に筆記試験。受講生全員が合格
排泄(はいせつ)介助の実技も習い、いよいよスクーリングも終盤。実技が身についたかどうか、2回のテストが行われました。課題は「ベッドから車椅子への移動・移乗」と「ベッド上のおむつ交換」です。講師の先生の前で、受講生一人ひとりが実技を行い、評価を受けます。評価ポイントは、習ったとおりの手順、動作で行えているか、利用者さん(要介護者)に適切な声かけができているか、といったことです。
テストの前には練習の時間をもらえました。1つひとつに細かい手順があるのです。端座位(たんざい:ベッドの端に座った状態)から車椅子に移乗する際には、まずはベッドの高さを下げ、利用者さんには靴を履き、浅座りし、足を開いてもらい、ひざ下を少し手前に引いて…と、どれも飛ばせない、前後できない工程です。頭で覚えようと思っても難しく、何度も練習して体に覚え込ませる必要があります。
とはいえ、これまでの授業でくり返してきたことの総決算であり、新しく覚えることはありません。練習後、受講生全員が問題なくクリアできました。
そして迎えた最終日には、筆記試験がありました。これがまさしく最終テストです。内容は、自宅学習で課題になっていたことが大部分。問題も3択で、7割解ければOKです。
実技のテストはすでに合格し、出席時間も満たしているので、この筆記試験に合格すれば、晴れて研修修了です。
筆記試験が終了すると、事務局の人がやって来て、その場で採点を始めました。そして、「みなさん全員合格です! おめでとうございます。正式な修了証書は後日お送りします」。
やったぁ! がんばりました。教室内は拍手。
週1回とはいえ、2カ月半、この教室に通い続け、一生懸命実技の練習をしました。10回分のスクーリングを思い出し、感慨もひとしおです。
副業の際、本業の稼働日が1日減るのは大変 予行演習で明確に
スクーリングの間、本業の編集者の仕事は、1週間のうち稼働日が丸々1日減ることとなりました。正直言って、なかなかきつかったです。平日4日では仕事が終わらない…。休日も使い、なんとか乗り切った格好です(職場は裁量労働制で、時間の制約はありません)。
スクーリングで週1日を使うのは、将来、副業を始めたときの予行演習でもありました。こんなに忙しくなるなら、副業は厳しい?
実は、もともと半日だけを副業にあてるつもりだったのです。1日ごっそり稼働日がなくなるのと、半日分は残るのとでは全然違います。半日ならなんとかなりそう。
反対に言えば、副業に丸1日はあてられない、半日がせいいっぱい、ということが明確になりました。実際に副業をスタートする前にわかってよかった。その点でも有意義な研修となりました。
受講前と後でガラリと変わった介護職のイメージ
介護職員初任者研修を受講した結果として、介護スキルの基本を習得できたのはもちろんですが、とても大きかったのは、介護と介護職に対するイメージがガラリと変わったことでした。
思い返せば、受講を申し込み、教材が届いて、まず最初にワークシートに書き込みをするようにと指示がありました。

お題は、「介護のイメージ」と「介護職とはどんな仕事だと思うか」。
研修を受ける前、予備知識のない段階で、率直に感じたことを書きました。
あらためて見返すと、「介護はとにかく大変そう」というところに意識が向いていました。
介護人材が不足している今、「多くの人がやりたくない、でも必要な仕事、だったら私がやらなきゃ」。家族が介護するのは大変だから、「助けてあげたい…」。ちょっと上から目線な、「介護をしてあげる」というスタンスでした。
介護すること、介護する側にばかり目がいき、「介護される側」への視点がすっぽり抜けていたのです。
そんな私のような人も多いのでしょうか…。講義ではくり返し、「利用者さん主体」ということを教えられました。
介護者のペースで介助をするのではなく、利用者さんの意志を確認しながら進めていく。何でもかんでも介助してしまうのではなく、利用者さんが今もできること=残存機能を活かして、自分でできることは自分でしていただく。利用者さんの立場になって、されたくないこと、言われたくないことは避ける…。
実技で利用者さん役をするのも、「利用者さん主体」の重要性を実感レベルでつかむことが、大きな目的だったと思います。
最終日、
「最初にご自分で書いたワークシートを振り返り、研修を受けた今はどう感じているか、書いてみてください」
と講師の先生から指導を受けました。

「何でもやってあげる」お世話係ではないのだと、「できないことをお手伝いする」サポート役なのだと、私の中ではっきりとした介護職像ができあがりました。
「介護をしてあげる」というおごった気持ちは消え、「介護をさせていただく」という謙虚な気持ちになり、介護職としてのホスピタリティー、基本精神が刻み込まれました。それこそが、この研修の最大の目的だったのではないかと思います。