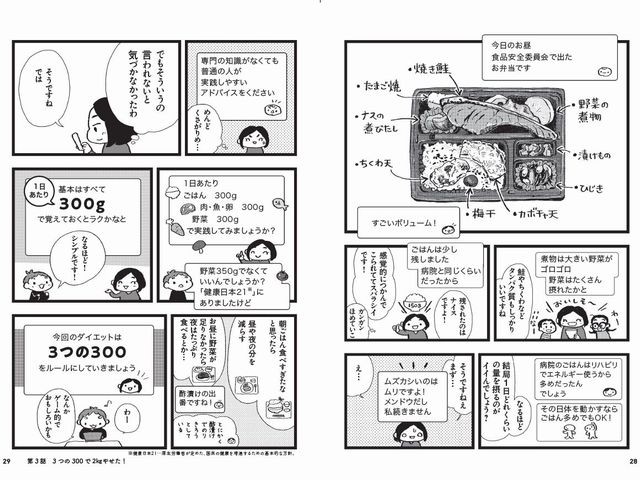小学生が「認知症」を体験……その時、教室で起きたこと
金澤ひかり (朝日新聞記者)

認知症の人の視点を小学生が体験したら? 「階段の段差がわからへん」「おばあちゃんこんな気持ちやったんやな……」。そして「いつも通り生きてるだけ」。仮想現実(バーチャルリアリティー=VR)の最新技術を使った教室では、予想外の小学生らしい発見がありました。
6年生40人が体験
VRで認知症を体験したのは、大阪市立大空小学校の6年生40人です。 授業では、まず、大阪市北区社会福祉協議会のコミュニティーソーシャルワーカー2人が認知症について説明しました。
講師の山本久美子さんは「最近の子ども達は、認知症という言葉は知っているものの、核家族化で同居している家族が認知症になるという経験が少なく、自分ごととして認知症を捉える機会が減っています」。そんな子供達にはまず、「認知症」自体を正しく理解してもらい、その授業を受けたという経験を持ってもらうことに主眼を置きたいとのことでした。

〈認知症〉
厚生労働省研究班によると、65歳以上で認知症の人は2012年時点で約462万人。いくつかのタイプがあり、記憶障害が典型的な症状の「アルツハイマー型」が最も多く、7割近くを占める。脳出血など脳血管障害が原因の型が2割ほど、幻視などを伴う「レビー小体型」が4%ほどとされる。高齢化で25年には高齢者の5人に1人の700万人に増えるとみられている。65歳未満で発症する若年認知症の人も09年発表の厚労省調査で推計約3万8千人いる。
「みんなも欲しいもの、何度も繰り返すでしょ?」
山本さんの話の中で、特に子どもたちが反応を示したのは、山本さんが「みんなはクリスマス前には、何度も欲しいものをお父さんお母さんに伝えない?」と聞いたときでした。
子どもたちは山本さんの問いに大きくうなずき、その続きに耳を傾けました。
「みんな、大切なことだったり、言ったか不安になったりするときに、何度も同じことを言いますよね。認知症の人も同じです」と山本さん。
「ほかにも、認知症の人は、さっき食事をとったのに忘れてしまって、またごはんを食べたいと言うこともあります」と話すと、一人の児童が「質問!」と、すっと手を挙げました。
「忘れてしまうなら、記録しておけばいいんじゃないですか?」
山本さんは少し考えてから「みんな、宿題やろうと思っているときに『宿題やりなさい!』と言われたり、頭ごなしに言われたらカッとするでしょう?誰でも決めつけて言われるのはいやなものです。決めつけずに、まず聞いてほしいなと思います」
山本さんは、講義を通して「認知症の方がいたら、手助けをしてほしい」と何度も繰り返し伝えました。

ハコスコを手にわくわく
認知症の人への接し方などを学び、さあVR体験です。
子どもたちは「なあ、VRって知ってる?」とわくわくした表情。
段ボールの箱に、VR動画を映し出すスマートフォンを設置した「ハコスコ」を両手で持ち、音声ガイダンスに沿って3分程度のVR動画を見ます。

認知症VRでは三つの体験ができます。
①自分のいるところが分からなくなり道に迷う
②階段を降りようとするが高低差が分からない=空間認識の欠落
③自宅のリビングに見えるはずのない女の子が見える=幻視症状
子どもたちはハコスコをのぞき込みながら、口々に「高さがよくわからなくない?」「歩きにくい」「みえないはずのものが見える」などと感想を言い合っていました。

認知症の曽祖母の「つまずき」理解した
階段を下りる体験をしたある児童は「そらおばあちゃんもつまずくわ」と口にしました。授業を見学にきていた、その児童の母親によると、児童は認知症の曽祖母(98)と同居しています。最近は自宅で、「よさそうなお店やな」と、実際にはそこにいないはずの友人とお茶会をしていたり、夜中にトースターでパンを焼いたりしているそうです。
児童の母親は「登校前、息子は『今日は絶対行かなあかん』と本人が言っていました。学びたいという意識があるんだなと感じました。今日の学びも踏まえ、おばあちゃんが楽しい日々を過ごせるようにこれからもサポートしたい」。

「寄り添い、相談に乗れるように」
このほかにも、児童からは「VRで階段を下りる体験をしたけど、高さがわからなかった。リアリティーがあって、認知症の人の気持ちが分かった」という声や、「VRでは(道に迷っている場面で)急に後ろから呼ばれて怖かった。認知症の人に寄り添ったり、相談に乗ってあげたりしたいと思った」という感想が聞かれました。

認知症の人、どういう思いで生きている?
VR体験後、子どもたちは数人ずつのグループに分かれ、「認知症でつらい思いをするのは誰だろう」「困っている認知症の人がいたら何ができるだろう」「認知症の人はどんな思いで生きていると思う?」という三つのテーマで議論し、発表しました。
子どもたちの感想で目立ったのは、「認知症の人はどんな思いで生きていると思う?」の問いへの答えでした。
「いつも通りに生きている」「いつも通りだから、普通に接してほしい」「割と楽しく生きている」などと、認知症の人の生活は特別大変なことではなく、普通の生活だという視点での発表が多くありました。
98歳の認知症の曽祖母がいる児童の母親は「大人だと大変だと思うことを子どもはそうはそうは思わないのかもしれないですね」と話します。以前、児童に「おばあちゃん何回もおんなじ話をしてくるね」と話しかけたところ、「何回も答えたったらええやん」と返事が返ってきたときにも、そう感じたそうです。
講師の山本さんは「子どもたちからは、高齢者の感情を汲み取った意見が多くあったように思います」。