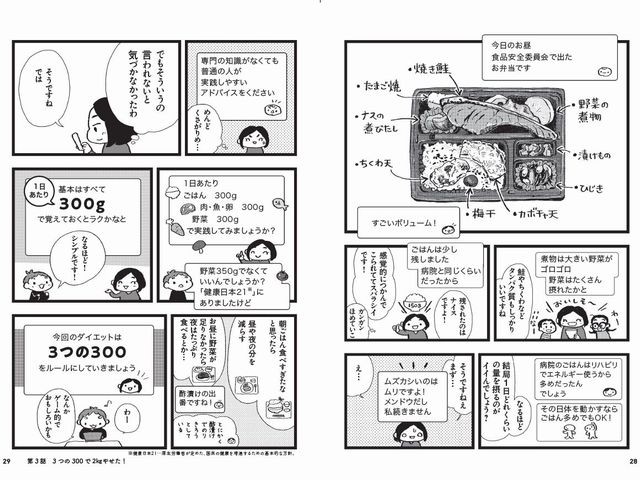「かんでもいいですよ」 問題と思われるような行動を安心に変える中間点とは
《介護福祉士でイラストレーターの、高橋恵子さんの絵とことば。じんわり、あなたの心を温めます。》

「いたっ!」
田中さんが今日も、
訪問介護ヘルパーの私の肩をかんだ。
百歳近いご高齢で、認知症も進行し、
日常生活のすべてに介助が必要な田中さんにはかみぐせがある。
口もとになにかが触れそうになると、
反射的にそれを、強い力でかんでしまうのだ。
色々な方法を試してみてもそれは変わらず、
ご家族もヘルパーたちも、疲れ果てていた。

田中さんはたまに「あー」などと声を出されるだけで、
意思の疎通は難しく、寝返りも打てない。
そうやって最期のときを、
穏やかに過ごされている田中さんなのに、
かみぐせがあることで、
ご家族も私たちヘルパーも、
気持ちが暗くなるのを止められなかった。
どうしたら、田中さんにかむのをやめてもらえるのだろう?

でもある時から、皆が変わった。
「田中さん、かまないで」から
「かんでもいいですよ」になった。
私たちヘルパーの体と
山田さんの口が触れそうになるときは、
タオルを使って対応した。
そうして、安心がうまれた。
——私にも、そしてきっと田中さんにも。
意志の疎通も難しくなった、最期の時を過ごされているような人が、
排泄(はいせつ)物を触っているのを目の当たりにしたり、
その人に脈絡なく体をかまれたりすると、
「なんとかやめさせなければ!」と必死になるものです。
私がはじめてそのようの行為に接したとき、
理解できないがゆえに恐怖にも似た感情が湧いたのを覚えています。
今思えば、私がどれだけ、人生の締めくくりの時を最後の力で過ごされている人を
自分のもっている常識にとじ込めようとしていたのかと悔やまれます。
視野が狭かったのは、私のほうだというのに。
というのも、介護職員となった私が、
多くの方々の「常識からはずれるであろう行為」に接し続けたのちは、
大往生を迎えようとしている方々を前にして、
常識などささいなことか、という、
力の抜けた感情に変わっていったからです。
これは長年介護を続けていらっしゃるご家族さんや介護士さんにも、
なじみのある感覚ではないでしょうか。
常識のメガネを外したとき、人の自然体は、人それぞれ。
自然に出てしまう行動を、無理やり止められることほど、つらいことはありません。
だから、問題と思われる行動を止めさせようと奮闘するより、
その行為の理由がどうしてもわからなければ、
お互いが安心して過ごせる中間点を探したほうがよっぽど、貴重な最期のときを気楽に過ごせます。
私たちは例外なく、誰もが老いてゆきます。
例えば、老いてぼけたその時に私がかみつこうとしていたら、
「かんでもいいですよ」と
声をかけてもらいたいと願うのは、私のワガママでしょうか?